ADOLESCENCE.思春期の相談について
大人になる準備段階の時期です。ホルモンの変化により体調を崩すことはよくあります。頭痛、朝になるとおなかが痛い、なんとなく体がだるい、朝起きられない、夜なかなか眠れない、などは思春期のお子さまによく見られる症状です。
まずはご相談ください。
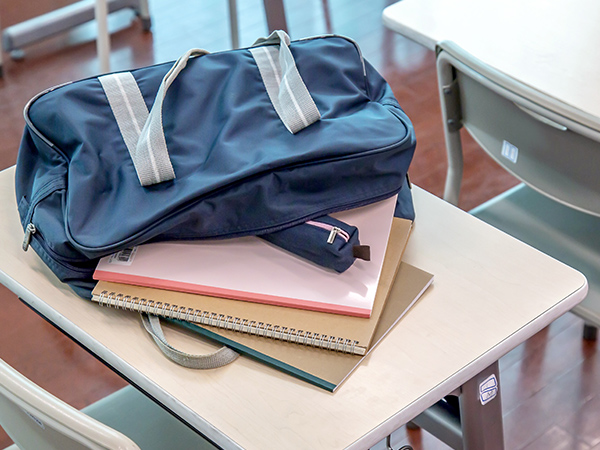
こんなお悩み
ありませんか?
思春期のお悩み
朝起きられない・夜眠れない


〈思春期に入ってから〉
- 朝起きられなくて学校にいけなくなった
- なんとか行けているが遅刻がち
- でも夕方になると元気になる
- 立ちくらみがでる
- 気持ちが悪い
- 頭痛がつづく
- 体がだるくてたまらない
- 立つことができない
- 横になっていると大丈夫だが座ると症状が悪化する
- 朝おきられず昼過ぎまでねていて、昼夜逆転し夜眠れない
上記症状が出てきた場合、まず睡眠時間を見直してみて下さい。
コロナ禍では起立性調節障害のお子さんが急激に増えた時期もありました。最近上記症状で起立性調節障害を疑い当クリニックを受診される患者さんが増えました。お話を伺うとほとんどのお子さんが睡眠不足です。睡眠を十分とるようなると、薬も使わずに軽快していきます。
こどもが必要とする睡眠時間は以下の通りです。(出典 科学技術振興機構 Sience Portalより)
- 1~2歳児は11~14時間
- 3~5歳児は10~13時間
- 小学生は9~12時間
- 中学・高校生は8~12時間
中高生なら、朝7時に起きないと学校を遅刻するというのであれば前日夜は遅くても11時には、布団に入って寝てないと睡眠不足という事になります。
お子さんたちの睡眠は十分でしょうか?
- 3食栄養バランスのとれた食事をとる
- お風呂に入って疲れを取り、夜十分睡眠をとる
これが一番の治療となります。まず生活を見直してみてください。
〈睡眠について〉
早く布団にはいっても眠れない場合,寝ているのにいつも眠いだるいという場合は睡眠障害の可能性もあります。
睡眠障害には発達障害によるもの、アデノイドの肥大やひどい鼻炎による鼻閉などの耳鼻科疾患、睡眠リズムの障害、足の違和感(足ムズムズ症候群)などの疾患が隠れている場合もあります。睡眠時間は確保しているのに昼間眠いやだるいなどの症状があるときは相談してください。
睡眠に関する資料 厚生労働省から専門家の書いた資料が載っています。
日本人の睡眠不足は非常に問題になっています。こどもからお年寄りまで睡眠について詳しく書いてあり、お子さんだけでなく親御さんの睡眠健康にも参考になると思います。
出典:厚生労働省出典
繰り返す頭痛や腹痛


〈頭痛について〉
「頭痛の原因は何か」、「どうすれば頭痛がよくなるか」、「命を脅かす病気は無いのか」を念頭に入れながら診察していきます。画像検査が必要と判断した場合は画像診断のできる施設へ紹介します。
繰り返す頭痛として代表的な頭痛の2つのタイプとして片頭痛と緊張型頭痛とがあります。
- 片頭痛
発作性にはじまり、2~72時間継続する血管の拡張に伴う拍動性の激しい痛みです。吐き気や嘔吐を伴い、光過敏、音過敏、臭い過敏といった症状もみられます。頭痛の「前兆」として、目の前にキラキラした光が見える人もいます。身体を動かすと増悪し、寝すぎると出やすいなど、週末寝坊をしたりすると出現します。 - 緊張型頭痛
年長児に多くみられます。慢性的な痛みで拍動性が無く、身体を動かしても変化しない、心身の緊張に伴う、肩こりを合併するなどの特徴があります。また、寝不足などで起こりやすくなります。 - 薬物乱用頭痛
頭痛もちの方が鎮痛薬を月に10日以上、あるいは週2~3日以上を毎週の様に服用していると起こる頭痛です。薬局で市販されている鎮痛薬でも比較的起こし易く注意が必要です。
〈自宅でできる頭痛予防〉
- 休日も平日と同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを心がけましょう。
- 夜は暗く静かな部屋でゆっくりと休みましょう。
- 寝る前2時間はスマホをやめましょう。
- 高過ぎる枕は避けましょう。
- 定期的に体を動かしましょう。
以下をヒントにご自分の誘発因子をさがしてください。
- 精神的因子:ストレス、精神的緊張、疲れ、睡眠不足、睡眠過多(昼まで寝ている)
- 内因性因子:月経周期(月経の始まり 排卵前後など)
- 環境因子:天候の変化(気圧の変化)、温度差、激しい運動、人ごみ、におい
- 食事性因子:空腹(低血糖)、ベーコン、ソーセージ、チョコレート、チーズ、カフェインのとりすぎ
〈くり返す腹痛〉
以下の症状がある場合はすぐに精査が必要となります。
- 右下または右上腹部痛
- 嚥下困難
- 遷延性嘔吐
- 消化管出血
- 炎症性腸疾患や消化性潰瘍の家族歴
- 眠りを妨げる夜間の腹痛
- 夜間の下痢
- 関節痛
- 肛門病変・口内炎
- 体重減少
- 発育遅延
- 思春期発来遅延
- 不明熱(熱源のわからない発熱がつづく場合)
明らかな上記徴候がなく、腹痛を繰り返す場合、代表的なものに、年少児に多い反復性腹痛(Recurrent abdominal pain:RAP)と、思春期以降に多い過敏性腸症候群(Irritable bowel syndrome:IBS)があげられます。
- 過敏性腸症候群について
過敏性腸症候群は成人ではよくみられる疾患です。大事な会議の前やテスト前などストレスを感じるとおなかが痛くなってトイレに駆け込むというエピソードを耳にしたことは皆さんありませんか。
原因は完全に明らかにはなっていませんが、腸脳相関の異常が大きくかかわっているといわれています。ストレスが下垂体でストレス関連ホルモン(CRF:corticotropin releasing factor)を産生させ、中枢神経を介して腸管神経系に働き、消化管の運動異常をおこし、便通異常を来します。さらに、消化管の内臓知覚過敏や知覚閾値を低下させ、腹痛を感じやすくなります。腹痛頻度や程度がひどくなることからお腹が痛くなったらどうしようと不安が増大し、それがストレスとなり腸と脳で負の連鎖が繰り返され症状が慢性化していきます。
不登校の原因の一つとなる場合もあります。
〈診断〉
下記のすべての項目があること。
- 腹部不快感(痛みとはいえない不快な気分)または腹痛が、下記の2項目以上を少なくとも25%の割合で伴う。
a)排便によって症状が軽減する
b)発症時に排便頻度の変化がある
c)発症時に便形状(外観)の変化がある - 症状を説明する炎症性、形態的、代謝性、腫瘍性病変がない。
2ヶ月以上前から症状があり、少なくとも週1回以上、基準を満たしていること。
〈治療の第一歩〉
正常排便のメカニズムをよく理解し、そのイメージをしっかり持ち毎朝十分な時間をとってトイレにいきましょう。
食事・生活リズムを整えることが大切です。排便日記をつけると客観的にみることができます。
何がストレスになっているのかを考えてみることも大切です。
上記でうまくいかない場合、症状が強い場合は内服薬も併用します。
- 正常な排便のメカニズム:食物が胃に入る刺激によって、便塊を肛門側に送り出す強い蠕動(ぜんどう)が結腸に起こる反応(胃結腸反射)がおこり、便塊が直腸に至り、直腸内が一定の圧に達すると便意が生じ、肛門括約筋の弛緩(直腸肛門反射)がおこり便が排泄されます。胃結腸反射は毎食後に起こりますが、通常は朝が最も強く出現し、この際に排便が行われます。
